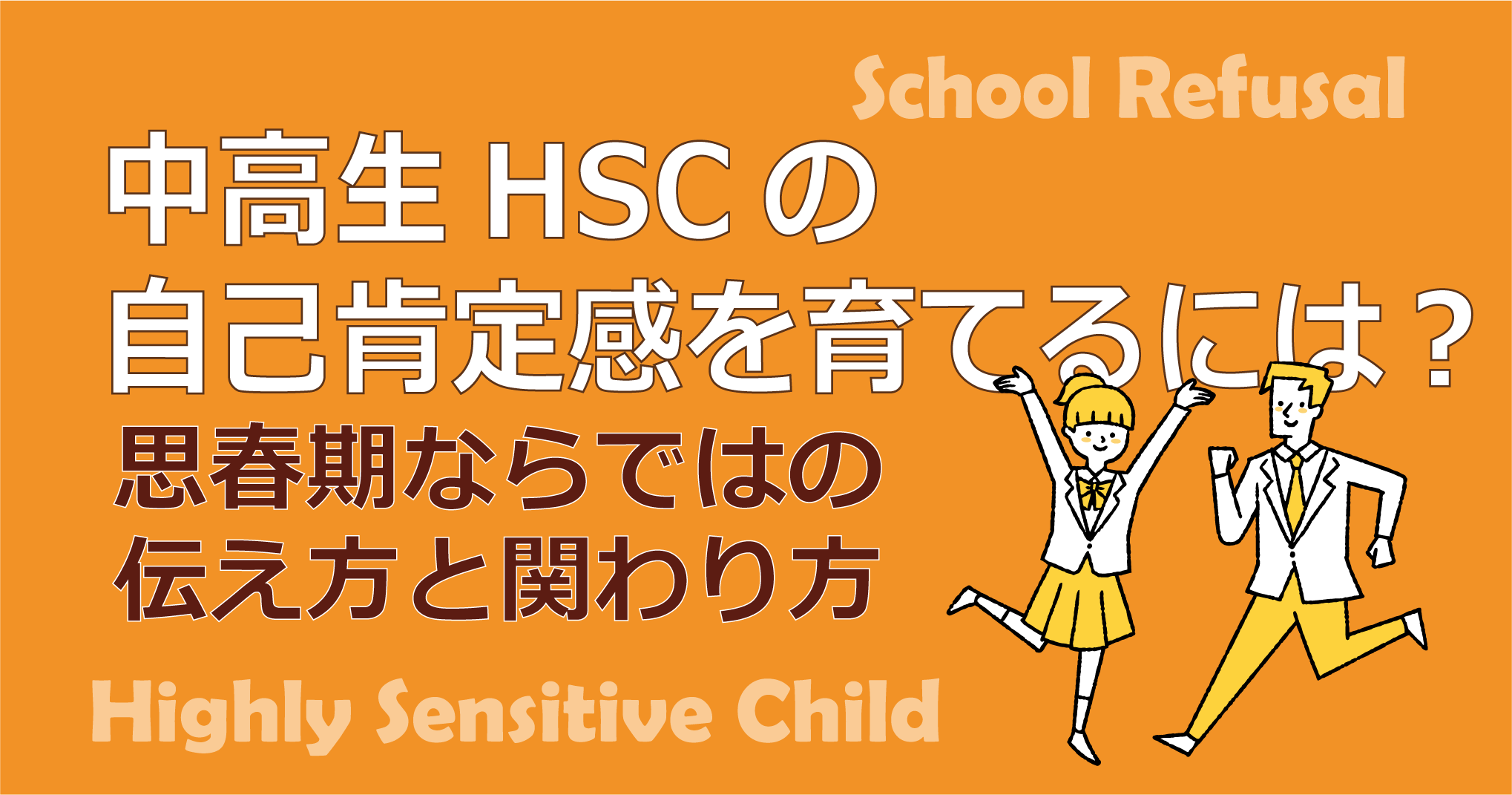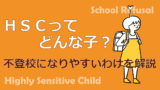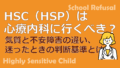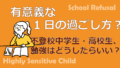思春期の自己肯定感を育てる難しさ
HSC――繊細で感受性豊かなこの気質の子育てでは、自己肯定感を育てることが大切。
これは多くの専門家も指摘しており、「常識」と言っても過言ではないでしょう。
自己肯定感があることで、HSCの子は傷つきやすさを抱えながらも、自分らしさを守りながら社会と関わることができます。

自己肯定感を育てるってどうやって?
たとえば、「否定や比較をしない子育て」は、もっともよく言われる方法ですが、それが活きるのは小さいうちのことかもしれません。
中高生ともなると、なかなか難しくなります。
その背景には、自己否定が長期間にわたって積み重なり、「自分には価値がない」という思い込みが潜在意識レベルで根づいてしまっているからです。
しかも思春期は親との関係が微妙で、声掛けが響かない、また伝え方ひとつで心を閉ざされてしまうこともあります。

そこでこの記事では、思春期のHSCに自己肯定感をどう育てるか、その方法と伝え方のコツをお伝えします。
自己肯定感とは自分を大切に思うこと

自己肯定感とは、いったいどういうもの?
自己肯定感とは、自分の存在や価値を肯定的に受け入れる感覚のことです。ありのままの自分を認め、大切に思える心の土台です。
文字通り、自己を肯定することであり、自己受容ともいえます。
よく、自己主張が強くて自信満々な人に対して「自己肯定感高いね」と言われることがありますが、それは皮肉や嫌味を含んだ言い方で、本来の意味とはズレています。
心理学者のカール・ロジャーズは、
「自己肯定感とは、ありのままの自己を価値あるものと感じること」
と定義しています。
自己肯定感とは、自分に不相応な自信を持つことではありません。
もっといえば、 「自分のことを嫌い」という自分を、そのまま認めることも、立派な自己肯定の一歩です。

つまり、「できる自分」でも「できない自分」でも、“今ここにいる自分を尊重できている”ことが自己肯定感の核心なのですね。
できないことを尊重するとは、「このままでいい」と開き直っていいという意味ではありません。
あくまで自己肯定感とは自身を「認めること」であり、その行為は、次の選択を可能にします。
・「だから努力して変えていこう」になるのか
・「今は無理だけど、それでも私は私でいい」となるのか
その先は人それぞれであり、どちらが良い・悪いという問題でもありません。
どちらを選んでも、“自分で選ぶ”という主体性が自己肯定感につながります。
HSCはなぜ自己肯定感が低いの?

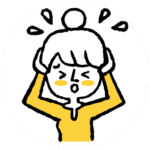
とくに比較や否定をして育ててきたわけではないのに、、なんでこんなに自己肯定が低いの?
やっぱり親である私のせい?
そう考えてしまうことは私もありました。
しかし、自己否定しやすい気質が土台にあるので、ちょっとした言葉で傷つくこともあり、特に親の育て方がわるいというわけでもないのです。
HSCは、自己否定しやすい特性
HSCはそもそも、親として特に問題のある子育てをしてなくても、自己肯定感が削がれやすい気質なのです。
それは以下のような理由からです。
人の事情や感情をくみ取り過ぎるため
HSCは、なにかよくないことがあってもそれを人のせいにしにくい性質があります。
共感力が強いため、相手の事情や気持ちを必要以上に感じとってしまうからです。
その結果、

「自分がいけなかったのでは?」
「自分がなんとかすれば…」
と考えてしまい、自分を責める傾向が強くなります。
人の気持ちの奥を読むくせがあるため
HSCは、常に周囲に敏感に反応しているため、人の気持ちの奥を読みすぎてしまう傾向があります。
・「いいよ」と言われたときの一瞬の間が気になり、「本当はよくなかったのでは?」と考えてしまう
・表情や声のトーンを深読みし、「怒ってるのかも」「嫌われてるのかも」と思い込んでしまう
発した本人にとっては何気ない言葉でも、HSCはその裏を深く考え、ないはずの意図を読み取ってしまうことがあります。
| 否定していないのに否定だと感じるケース |
| 「気にしすぎだよ」 →「そんなあなたがよくないよ」と受け取ってしまう 「そんなこと気にしてるの?」 →「あなたはおかしい」と感じてしまう 「あなたが悪いなんてそんなわけないでしょ」 → 「悪いと思ってしまう自分がわるい」と思う” |
| 比較していないのに比較されたと感じてしまうケース |
| 「○○ができるってすごいね」 →「できない自分はだめなんだ」 |
このように、HSCの思考のくせが、実際には存在しない否定や比較を“ある”と受け取り、自己否定へとつながっていくのです。
学校という場所が自己肯定感をそぐ
また、日常的に多くの時間を過ごす学校という場所が、HSCの気質との相性がすこぶる良くないという点も大きな影響を与えます。
日本の学校教育は「同調」「評価」「比較」がつきものです。
HSCの子にとっては、集団行動や成績による順位づけが強いストレスとなり、

「私は普通じゃない」
「みんなと違う」
「できない自分はダメ」
といった思考に陥りやすくなります。
HSCは学校が苦手です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
そうした場所で一日の大半を過ごすことで、HSCの自己肯定感はじわじわと削がれていってしまうのです。
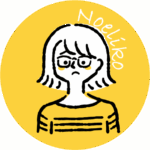
また、合わない環境で無理をしたり、自己否定を繰り返したりすると、心の病の心配も出てきます。
こちらの記事もぜひご覧ください。
自己肯定感があがるといいこと
自己肯定感が育つと、どんな子どもでも安定していきます。
HSCが人の気持ちを察したり、さまざまな感情を受け取ったりすることは止められません。そして、止める必要もありません。
問題は多くを感じ取るとこではなく、感じ取ったことで自己否定の思考が働いてしまうことです。
大切なのは、感じることで傷ついても、立ち直れる力を持つこと。
自己肯定感が高まれば、HSCの子どもは自分自身の素質と起こった出来事を切り離して考えることができるようになります。
HSCの子にとって、自己肯定感は“外の世界と安心してつながる”ための鍵となるのです。
自己肯定感を育てる子育ての基本
子育ての中で自己肯定感を育てるには、日常のちょっとした声かけや態度が大きな影響を与えます。
特にHSCのように敏感な気質を持つ子どもに対しては、以下のようなポイントを意識することが大切です。
| 否定しない | 「そんなこと思わないで」ではなく「そう思ったんだね」と受け止める |
| 比較しない | 「○○ちゃんはできるのに」ではなく「あなたはあなたのペースでいい」 |
| 条件をつけない | 「できたからえらい」ではなく「いてくれてうれしい」 |
| 結果より過程を褒める | 「がんばってたの、見てたよ」 |
| 安心できる居場所を作る | 「ここにいれば大丈夫」と思える空間と関係性 |
これらは、HSCに限らずすべての子育てにおいて大切なことですが、HSCに対しては特に意識しておくとよいでしょう。
こういったことを頭の片隅に置きながら、日常のなかで少しずつ声かけや関わり方を見直すだけでも、子どもの心に安心感と肯定感が育っていきます。
思春期版、自己肯定感の高め方

思春期の自己肯定感を育てるのは難しい、と最初にお伝えしました。
幼少期に有効だった「自己肯定感を育てる子育ての基本」が、まったく意味をなさないわけではありません。
しかし、思春期に入るとより根深く、潜在意識レベルで“自分の価値が低い”という思い込みがこびりついていることが多く、これだけではなかなかの長期戦になると考えたほうがよいでしょう。
思春期のHSCにより効果的な方法として、「自己肯定感を意識するのではなく、“自分軸”を意識する」という視点をおすすめします。
思春期には「自分軸」から整える

思春期のHSCには、ただ「自己肯定感を上げよう」とするアプローチだけでは届きにくいことがあります。
そこでカギになるのが、「自分軸」の形成です。
自分軸を形成するのには次のようなステップで進めていくとよいでしょう。
自己肯定感は意識しすぎない
HSC自身も、自分の自己肯定感の低さを「このままでいい」とは思っていないはずです。
でも、どうしても自分に価値を感じられない――その状態は、理屈ではなく潜在意識の中に根を張った“思い込み”として存在しています。
そして、自己肯定感を「持たなきゃ」「上げなきゃ」と思うこと自体が、“今の自分には自己肯定感がない”と否定することにつながり、さらに落ち込んでしまうというジレンマが生まれます。
まずは「今の自分はそうなんだ」と受け入れ、無理に高めようとせず「そうなれたらいいな」と思うだけで十分です。
自分自身への信頼を回復していく
次のステップは、自分に対する信頼を回復すること。
具体的には以下のポイントを意識して生活してみましょう。
たとえば、友達とランチに行くとき、「何食べたい?」という話になったとします。
そんなとき、

なんでもいいよ
といいがちなHSC。
「なんでもいいよ」この言葉の裏側に以下の思いがあるのはよくありません。

自分の意見言うなんておこがましいから…考えなくても(決めなくても)いいか

本当は中華は嫌なんだけど、空気が悪くなるからいうのは我慢しよう
「なんでもいいよ」そういったとしても、それを「自分で考え」「自分で決め」「自分の思いを大切にして」いるのならOKです。

今食べたいのはイタリアンだな。でも他もそんなに嫌じゃないからなんでもいいな

中華は嫌だけど、チャーハンなら食べたいかも。なら別に大丈夫かな
同じ言葉でもきちんと自分の思いに立ち返り、場の流れでなく自分で考え決めるという行程を大切にしてみましょう。

いきなり自分の意見をはっきり言えなくても大丈夫です!
以上のポイントを意識して行動することを日常の中で少しずつ増やしていきましょう。
そうすることで「自分で考えられた」「自分で判断できた」という成功体験が積み重なっていきます。
このプロセスが、潜在意識にこびりついた自己否定の思い込みを、少しずつ塗り替えていくのです。
あらためて、自分軸とは?
「自分軸」とは、自分の考え・価値観・感情をもとにして物事を判断し、行動できる状態のことです。
他人の評価や期待に左右されず、「自分にとってどうか?」を基準に選択できる感覚ともいえます。
たとえば、こんな違いがあります
| 自分軸 | 他人軸 |
|---|---|
| やる価値があると思うからやる | 怒られるからやる |
| 自分がやりたいからやる | みんながやっているからやる |
| 自分の思いで行動する | 他人の顔色を窺って行動する |
勘違いしてはいけないのは、「他人のために動く=他人軸」ではないということです。
誰かのために何かをするという選択を“自分の意志で決めた”のであれば、それも立派な“自分軸”です。
たとえば、
友達にノートを貸して、と言われ

嫌だけど断ったら怒るだろうな…
と考えて貸すのは他人軸です。
しかし

あんまり気は進まないけれど、この子は本当に困ってそうだし貸してあげたいな
と思って貸すのは自分軸です。
行動を起こすきっかけとなるのが自分の思いなら、自分軸で考えているといっていいのです。
そして自分の思いを大切にすることはいわゆる自分勝手・わがままとは違います。
わがままとは、自分の欲求・利益のために自分を押し通すことです。
大きな違いとしてはそこに「他者への配慮」があるかどうかです。
自分の思いを大切にしたいとき、そこに犠牲となる誰かや何かがあるのは、ある程度仕方のないことでしょう。
ただそうした相手があるときに、心から「ありがとう」を示す、今後何かあった時に力になる、誠心誠意説明して納得してもらう、などの行動をとることが大切です。
| 自分軸 | 自分勝手・わがまま |
|---|---|
| やる価自分の価値観・気持ちに基づく | 自分の欲求・感情だけで動く |
| 自分も相手も尊重する | 相手の気持ちは考えない |
即効性?潜在意識に直接働きかける方法
長年の自己否定が染みついている場合は、脳や潜在意識に直接働きかける方法も効果的です。
いわゆる「マインドトレーニング」のような手法で、HSCの子にも親しみやすく、日常に取り入れやすい方法をご紹介します。

なぜその方法が有効なの?
実は、脳は繰り返される情報にだまされやすい性質があります。
それを利用します。昔から「言霊(ことだま)」という言葉があるように、 「言い続けると叶う」というのは迷信ではなく、
言い続けることで脳がそれを現実として認識し、行動も変わっていくからなのです。
思春期版HSC 伝え方の極意
こうした自己肯定感向上プロジェクトも、本人のやる気がないと実行できません。
親を疎ましく思う思春期には伝え方にも注意が必要です。
| OK | NG |
|---|---|
| 対等目線「どう思う?」「やってみる?」 | 上から目線「○○しなさい」 |
| 雑談(提案)口調「試しにやってみるといいみたいよ」 | 相命令口調「あなたが困る!やったほうがいい」 |
HSCの子はとくに、圧をかけられると壁を作りがちです。
ですので、「教えてあげる」「導いてあげる」ではなく、 「一緒に考える」「あなたの感じ方を尊重する」スタンスが大切です。

反抗的な態度にも対等を意識すると響くことが多いので試してみて下さいね
おわりに:思春期HSCの自己肯定感は“自分軸”から
HSCの子どもにとって、自己肯定感は生きやすさの土台です。
しかし、思春期になると自己否定が深く根付き、親の声かけも届きにくくなります。
そこで、思春期のHSCには「自己肯定感を高める」ことよりも、“自分で考え、決める”という自分軸を育てるアプローチが有効です。
さらに、アファメーションやポジティブ記録など、脳や潜在意識に働きかける方法も、心の深い部分にじわじわと効いていきます。
ただし、これらすべては伝え方がカギ。
思春期のHSCには「上から目線」ではなく、「対等な関係性」での関わりが大切です。
提案口調で、そっと差し出すようなかかわりが、子ども自身の「やってみようかな」につながっていきます。
焦らず、比べず、見守りながら、少しずつでも「自分って悪くないかも」という感覚を取り戻していけるよう、
今日からできることを重ねていきましょう。

自己肯定感を育てるには自己理解も必要です。
こちらの記事をご覧ください。