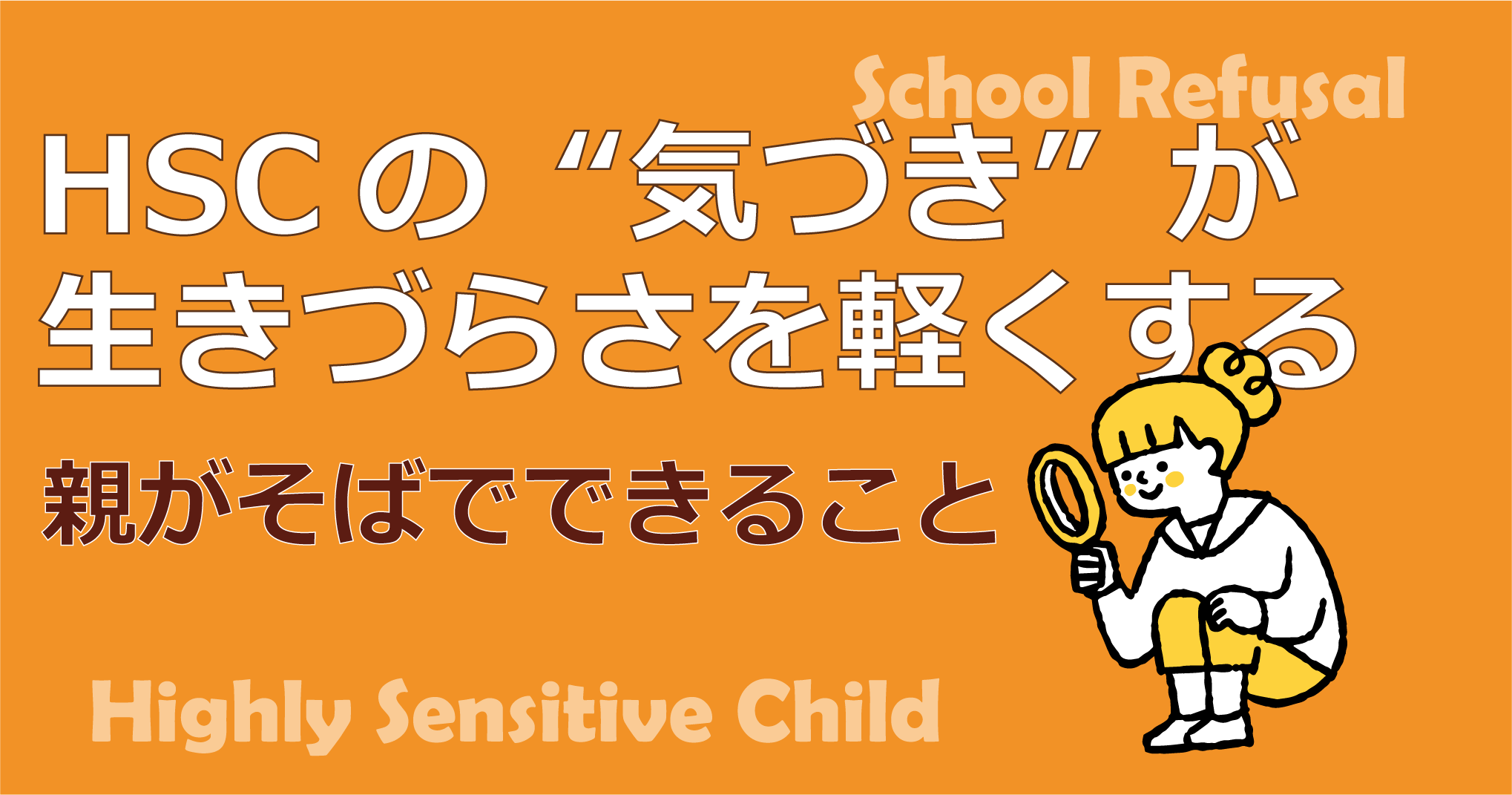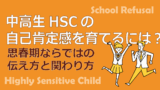HSCは“非HSPの感じ方”を知らない?
HSC(ひといちばい敏感な子)は、さまざまな刺激に対してとても敏感に反応します。
HSCが生きづらさを感じる大きな理由の一つが、非HSPとの「感じ方のちがい」です。
非HSPにとっては何でもない音が、HSCには耳をふさぎたくなるほど不快に感じられる――
たとえば花火を見ているとき
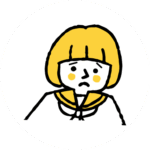
音が怖すぎて楽しめない…

え?そんなに?花火を見ていたら気にならないけど
ここには、感じ方のちがいがあります。
HSC自身、そうしたちがいに悩むので、ちがいが存在していることには気がついてます。
ここでは、HSCが非HSPとの間にある「感じ方のちがい」のその大きさに気づくことが、自分を理解する第一歩になる、というお話をしたいと思います。
・なぜHSCが“非HSPとの感じ方がどれくらいちがうのかを知る必要があるのか
・それがどう「生きやすさ」や「自己理解」につながるのか
を、この記事でお伝えしていきます。
HSPにとって自分の感覚が「普通」

繊細な子どもたちは、なんとなく
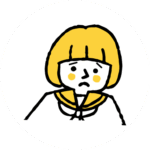
自分はまわりと違うかもしれない
と感じています。
みんなが平気そうにしているのに、自分だけが強く反応してしまう……
その“感じ方のちがい”が、自信をなくすきっかけとなり、自己否定や自己肯定感の低下につながってしまいます。
HSCという気質を知れば、「自分は刺激に対して敏感なんだ」と理解はできます。
でも、「刺激に対して敏感」とは、具体的にどういうことなのでしょうか?
問題はそこにあります。
一般と比べてどれくらい「敏感」なのかがわからないのです。
たとえば、目が悪くなったと気づけるのは、もともと「よく見えていた状態」を知っているからです。
しかしHSCの気質は生まれながらにしてのもので、急に感受性が強まったわけではありません。
ずっと“敏感な感覚”で生きてきたため、自分の感じ方が「普通」だと思っているのです。
でも実際の世の中で“普通”とされている感覚は、非HSPの人たち――つまり、HSCとはまったく違う感覚を持つ大多数の人たちによるものです。
そこに「感じ方の大きな差」があることに、HSC本人が気づく機会は意外と多くありません。
しかし、その「感じ方の大きな差」を知ることで、HSCはとても生きやすくなるのです。
「感じ方の大きな差」親がHSCに最初に伝えるべきこと
HSCが周りと違う自分に対して苦しんでいたら、親はまず、以下のことをしていくとよいと思います。
1.「感じ方の違い」があることを認める
2.どちらの普通も尊重されるべきだと伝える
3.お互いの普通に大きな差があると伝える
「感じ方の違い」があることを認める
まずは、「大げさに考え過ぎ」「気にしすぎ」という言葉で片づけることなく、感じ方が違うという事実があることを、認めてあげましょう。
「気になる」というHSCの感じ方を「そうなんだね」と受け入れるのです。
これだけでかなりHSCは安心感を覚えます。
これは失敗談なのですが、私は逆に、その繊細な感覚に対して
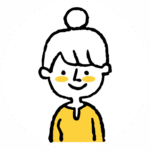
人と違うなんて、うらやましいよ!
といいました。…励ましたつもりでした。
非HSPの私から見れば、娘の繊細な感覚や少数派であることは特別で、魅力的にも思えたのです。
しかしそもそもHSCは、感じ方がちがう、のではなく自分の感じ方がズレている、自分の感じ方がへんだと感じるために、苦しんでいるのです。
人と違うこと=変なことを褒めても、何も響かないのは当然です。
「普通でありたい」と願っていた娘にとって、それは励ましではなく、悪口みたいなものでした。
今思えば、そのとき必要だったのは、ただ「そういう感じ方なんだね」と、ありのままを認めてあげることだったと思います。
すごいことでも、劣っていることでもなく、ただ「違いがある」という事実を、否定も美化もせずにみとめてあげること。
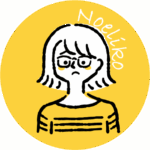
違っていていい、そういうことを伝えることがHSCにとっての安心になるのだと、今ならわかります。
どちらの普通も尊重されるべきだと伝える
それから、感じ方はそもそも人それぞれで違うことを伝えていきましょう。
例えば、ほぼみんなが大好きなピンク色を嫌いだった女の子。
みんなの人気だった給食の揚げパンが食べれられない子。
多数が好きでも誰かしら少数派はいたはずです。
その子たちが間違っていると思う?と聞いてみるといいと思います。
HSCは確かに少数派です。
感じ方は目に見えないので批判されることは多くなると思います。
けれど、ピンクが嫌いで揚げパンが苦手だった子たちのように、けして「間違い」ではないことを伝えることは大切なことです。
違いの大きさも、やさしく伝える
そしてその後、自分の想像以上に大きな「感じ方の違い」があることも、やさしく伝えてあげてください。
もしかしたら、そこでまた少し戸惑うかもしれません。
しかし、その“違いの大きさ”を知ることが、自分自身の感覚をさらに理解し、自分を守るための第一歩になります。
非HSPは本当に“気にならない”と知る大切さ
なぜ、“違いの大きさ”を知ることが、自分自身の感覚をさらに理解し、自分を守るための第一歩になるのでしょうか?
HSCの子どもたちは、ときどき「そんなこと気にしてるの?」という反応に傷つくことがあります。
非HSPの人にとっては、本当に“気にならない”から不思議なだけなのですが、HSCにはあまりピンときません。
とても強いな、努力してるんだな、と考えたりもします。
しかし、非HSPは我慢してるわけでも努力してるわけでもありません。
ほんとうにそもそも最初から気になっていないのです。
この事実を知らないと、HSCの子どもは、気になる自分が弱いのだと思い込み、何度も自己否定を繰り返してしまいます。
でも、自分とはまったく違う「普通の世界」がある(“違いの大きさ”がある)ことを知ると、こう思えるようになります。

「ああ、自分は弱いわけじゃなかったんだ」
「感じ方の強さがこんなに違うなら、そりゃ私は気になっても仕方ないな」
それは、自己肯定感の土台を築く大きなきっかけになります。

とくに思春期のHSCの自己肯定感の育て方についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています!
「わかってもらえない」孤独も少し軽くなる
また、自分がいかに敏感なのか知ることで、わかってもらえない孤独さも軽くなるでしょう。
そもそも、感じる強さが違うのです。
たとえば三人で会話しているとします。

なんかあそこ変な匂いしたよね?
「え?気にならなかったけど?」「なんも匂いなんかしなかったよね」
HSCの感じたものが、二人の同意を得られないという場面も少なくありません。
そうした時に

「変なこと言っちゃったかな…」
「言わなきゃよかった」
と、考えて落ち込んでしまいます。
共感力の強いHSCは自分が共感されることにもとても喜びを感じます。
でも、「そもそも伝わらなくて当然なんだ」と知ることができれば、その孤独は少しだけ軽くなります。
“共感してもらえない=自分が悪い”ではなく、ただ感じる範囲が違うだけだったと理解できることが、心の安心感につながります。
次のステップは感じ方の“すり合わせ”

感じ方が違うという前提で、次に親ができることは感じ方のすり合わせです。
感じ方のすり合わせをして、その大きさを自覚していくのです。
この作業は語弊があるかもしれませんが、私はとても面白く興味深いことでした。

HSCの感じている世界は、異世界でした!
娘にとっても、非HSPの感じ方を知ることは目からうろこの発見だったようです。
この感じ方のすり合わせをすることで自分の感覚だけで「事実だ」と思い込まないことが重要なのだと、お互いに感じました。
感じ方のすり合わせの具体的な方法としては以下のようなものです。
同じ事象に対して感情の度合いを示しあう
例えば①朝学校に行って友達が先生に怒られていたらどう思う?という状況を共有してみます。
HSC

そわそわする…自分のせいかもしれないと思う…
自分事
非HSP

なにしたのかなぁ?
他人事
たとえば、②映画を今から続けて2本見るとしたら?
HSC

疲れる…いろんな情報が溢れすぎて感情が忙しくて疲れる
情緒の問題
非HSP

疲れる…3時間はきつい…
体力の問題
③レストランで、隣の席と距離が近く、話し声が聞こえてきていた、そのあとの感想
HSC

隣の席の人がなんか悪口を言ってた。聞かないようにしようとしても聞こえてきてしまうので、嫌な気持ちになった…
気持ちにまで影響
非HSP

まぁたまに話す内容は聞こえてたけど詳しくは覚えていない・・雑音程度。そう言われてみれば悪口大会だったかも?
影響なし
いかがでしょう?これを読んだだけでも少しお互いの感覚の違いが分かりませんか?
感じたこと=真実? 正解を確かめてみる
HSCの子は、相手のちょっとした表情や仕草に敏感に反応し、「嫌われたかも」「怒ってる?」と考えてしまいがちです。
でも実際には、そうではないことも多いものです。
たとえば、

さっき、怒ってた?

え?全然。ただお腹空いてただけだよ
黙っていているだけで、わたしのことを怒ってるかな?と感じたHSCと、お腹がすき過ぎて無口になってしまっていた非HSPの会話です。
そんなふうに確認していくことで、「感じたこと=真実」とは限らないことを学ぶことができます。
これは親子だからこそできる、安心してできる“感情の確認作業”です。
感じ方のすり合わせで築くより良い関係
親子という関係は、もっとも身近で、もっとも安心できる練習の場です。
「お母さんはこう思ったよ」
「でもあなたはこう感じたんだね」
とすり合わせていくことで、認知がずれていたことに気づけます。
それは、親にとっても子どもを知ることになります。
HSCにとっては、

「気持ちを話してもいいんだ」
「わかろうとしてくれる人がいるんだ」
と感じられる大切な体験になり、気持ちを話す練習にもなります。
「感じ方の大きな差」伝え方には注意を

非HSPが刺激を「無意識にスルーしている」ことを知ると、自分の感じ方とのギャップがはっきり見えてきます。
しかし実はHSCにとってショックなことかもしれません。
自分が、はっきり他とは違うということを認識した瞬間でもあるからです。
そしてその気質が病気ではなく、治るものではないと知ってるからこそ、その事実が苦しく感じることもあるでしょう。
また、HSCは、言葉の奥の意味を深くとらえようとする傾向があります。
そういったこともあり、伝え方にはとても気を配る必要があります。
違いを知ることの意味までしっかり伝える
感じ方の違いが浮き彫りになることで、ショックを感じる子もいるようです。
こうした違いを知ることで、前向きな選択ができるのだと言う事までセットで伝えてあげてください。

娘もショックを受けていました。
一緒に考えていこうと思って伝えたのだという思いを添えるとよいと思います!
思いは否定しないように気を付ける
感じ方のすりあわせをするときも気をつけましょう。
HSPが「みんなが悪口を言っている気がする」といったとして、非HSPである親はついつい「そんなわけない」といってしまいます。
HSCはそこで口を閉ざしてしまうことがあります。
悪口を言っているなんて、そんなわけない、という意味なのですが、
HSCは、悪口を言ってると思うなんて、そんなわけない、と言われた気持ちになります。
つまり、悪口言われたと感じる自分が、否定された気持ちになるのです。
まずは、 否定ではなく、「そう感じるんだね。」と、認めることが大事です。
そのあと、「でも、自分はそう考えないな」と伝えていきましょう。
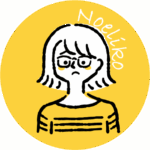
私はすぐ「そんなわけないでしょ!」とピシャリと言ってしまって、、大失敗しています!
今だから気づくことでもあります。
非HSPの視点を知ることで、HSPが生きやすくなる
このように、ショックかもしれませんが「感じ方の差」と知ると、本人の心の持ち方が変わってくることが期待できます。
HSCの子どもたちは、社会の中では“感じすぎる少数派”、いわゆるマイノリティにあたります。
一方で、刺激にあまり反応しない非HSPは、多数派=マジョリティです。
学校や社会の仕組みは、多くの場合マジョリティの感覚を基準につくられています。
そのため、HSCの子が「生きづらさ」や「違和感」を感じるのはある意味当然のことです。

以下のことを意識して、自分の感じ方を自分でも否定することなくうまく付き合っていけるといいですね。
感じすぎることは、止める必要はない
感じることを止めることはできません。
そしてそれを本当はたいしたことじゃないんだと思い込む必要はありません。
感じることは感じるままでよいのです。
ただ、次の段階で、あ、相手はそこまで感じていないのだなと「意識的なスルー」ができるようになればいいのだと思います。
たとえば、音や光のような物理的な刺激を無視するのは難しいかもしれません。
でも、人の感情や場の空気のような「情緒的な刺激」については、

「私は今、気になっているけれど、他の人はそこまで感じていないかもしれない」
「だから、きっと大丈夫」
そんなふうに、一歩引いて見ることができるようになると、ぐんと生きやすくなるでしょう。
それは今までの我慢とは大きく違うものです。
自分の感覚を尊重しながら、“気にしすぎない”方向に意識を向ける技術です。
理解は、自分を守る力になる
そして最終的に、こうした“違いの理解”は、自分で自分の困りごとを説明したり、対処したりする力へとつながっていきます。

「こういう場面ではこう感じてしまうんだ」
「だから少し離れる時間が必要なんだ」
そんなふうに、自分の生きづらさを“言葉にして説明できる力”がついていけば、まわりに助けを求めることもできるようになります。
違いを知り、自分を知り、相手を知ることは、HSCが自分を守りながら生きる力そのものになるのです。
正しくつらさを伝えられる能力を養うことはこれからさまざまなコミュニティで生きていくHSCにとってとても重要なものになります。
HSCの生きづらさは「感じ方の違い」に対する理解不足
HSP(HSC)の生きづらさは、実は「感じ方の違い」に対する理解不足から生まれていることが少なくありません。
自分自身がどんな刺激に敏感で、何に疲れやすいのか――そうした“自分の感覚”を理解することはとても大切です。
けれど、それと同じくらい重要なのが、「非HSPの感じ方を知ること」。
自分とは違う感覚を持つ人が、世界をどう受け取っているのかを知ることで、伝え方や距離の取り方が変わってきます。
そしてその“違いの大きさ“まで理解したとき、はじめて本当の意味で「自分を守る方法」が見えてくるのです。
他人との違いを知ることは、我慢することでも、合わせることでもありません。
違いを前提にしたうえで、自分らしく生きていくための知恵と力になるのでしょう。