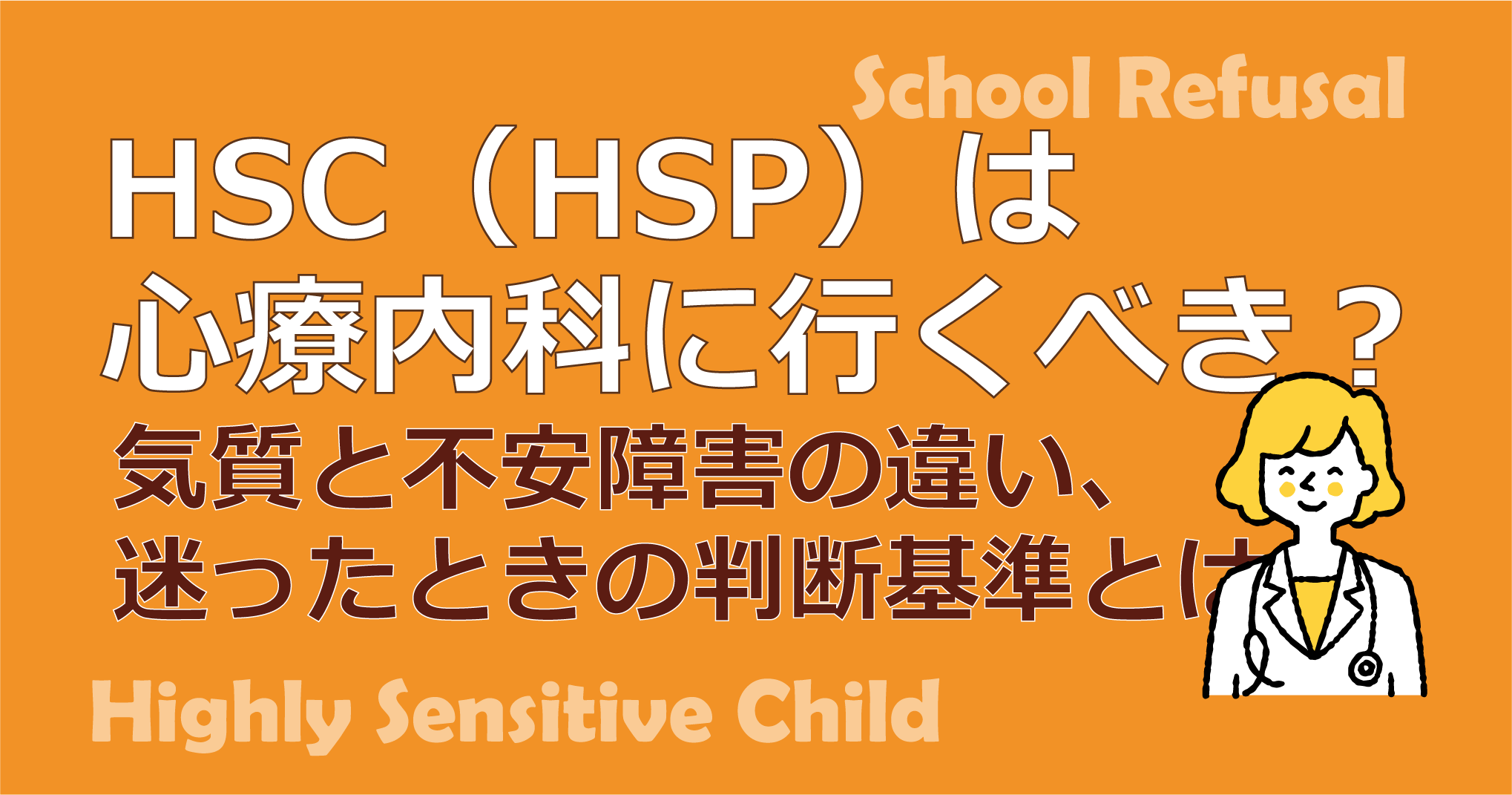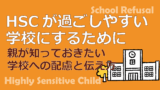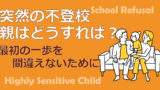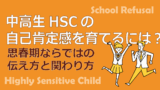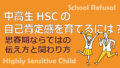HSP外来って行くべきなの?
最近、「HSP外来」や「HSPカウンセリング」を掲げる心療内科をよく見かけませんか?

え、HSPって受診した方が良いの?
HSPが病気でないと知っていても、そう思う方もいると思います。
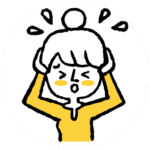
「気質であるHSP/HSCにやっぱり「診断」が必要なの?」
「放っておくと何か問題になるの?」
この記事では、「受診の必要性」や「心の病と気質の関係」について整理してみたいと思います。
HSP/HSCは病気ではないから安心?
HSC/HSPは病気ではなく、気質です。
治すものではないので、基本的に治療の対象ではありません。
気質とは・・・生まれ持った感覚の強さや反応の仕方の傾向を指します。
これは“性格”や“性分”とは異なり、育て方や経験で大きく変えることが難しいものです。
ではなぜ、心療内科にHSP外来があったり、HSP受診を勧める文言を見つけたりすることがあるのでしょうか?
実は、「自分はHSPの気質だから」と思って受診をためらう中に、
本当は心の不調や障害があるにもかかわらず、それに気づいていない人がいる
という背景があります。
HSC/HSPの気質自体は病気ではない、それは確かです。
しかし、気質のせいだと思い込んでいると、実は心の病だった、という可能性があるのです。
HSP/HSCの気質と不安障害の関係性
人は、どんな時に不安を感じるでしょうか
いつもと違う様子を感じたとき
先が見えない、見通しがつかないとき
など
不安とは、危険を察知し、身を守るための重要な感情だと言われています。
危険かもしれないと感じると、不安になる…これは、原始の時代から変わらない人間の生きるために必要な反応です。
HSPは危険察知能力が高く、原始の時代では生き残るための重要な存在であったとされています。

ちょっとした変化や刺激を感じることで危険を回避してきたHSP。
「危険をいち早く察知して、集団の生存率を高めていた」という仮説は、HSP研究の第一人者エレイン・アーロン博士も言及しています!
現代においても、さまざまな刺激や人間の感情、HSPはそれらを敏感に察知します。
もちろん、それらの刺激すべてが危険と言うわけではありません。
現代においては命を脅かすような危険に遭遇することは稀なことでしょう。
しかし、多くの刺激を自分を不安定にさせる危険要素だと認識することで、HSPは不安を抱える頻度は人より多くなります。
非HSPとくらべて、不安で不快な状態になることが多いといえるのです。
HSPは「炭鉱のカナリア」とも言われます。カナリアは空気の異変をいち早く感じ取るため、かつては炭鉱で安全確認に使われていました。同じように、HSPは小さな変化や刺激を人一倍敏感に察知します。
HSC/HSPの二次障害である不安障害やうつ

不安を抱えることの多いHSPが、その不安が解消されない状態、つまり、
・自己理解が進んでおらず、自分を否定ばかりする
・刺激の強い環境で無理をしている
そうした状態を続けていると、病気へと発展してしまうことがあります。
治療しないといけないのは、HSP自体ではなく、不安になりやすいHSP気質が引き起こす二次障害です。
HSC/HSPの気質と不安障害との線引き

病気になっているのに、気が付かない人がいるの?
そうなのです。
HSPの気質上、病気になっているのに見逃してまう危険をはらんでいます。
そもそも不安を抱えやすい気質である、というのが大きな理由です。
HSP/HSCは想像力がとても豊かで、ちょっとしたことで大きな不安を抱えることも珍しくありません。
そのため、不安障害になっているのか、気質特有の不安なのかの区別がつかないまま、病気を見逃してしまうことがあるのです。
たとえばHSPは
・明日忘れ物したら大変だと思うと、何度も鞄を確認したりする
・疲れ果てて消えてしまいたいと思うくらい落ち込む
・ほぼ起こり得ない心配をして眠れなくなる
ことは結構あるあるとして語られます。
これらの事象は、一時的なものですが慢性化してくると、不安障害的な要素です。
確認の回数が増えたり、他の行動にも確認作業が広がっていったりすると、強迫性障害の可能性があります。
消えてしまいたいと日常的に考えるようになると鬱かもしれません。
HSCが「心の病」に進む前に気づきたい危険サイン
困ったことに、HSC気質が不安障害の症状と境界線が曖昧なところがあります。
しかし明確に気質と病気には違いがあります。
気質と病気の境界線とはどういったところにあるのでしょうか?
「気質」と「病気」の線引き
ポイントは「日常生活に支障が出ているかどうか」です。
勉強、睡眠、人間関係、移動など、基本的な生活行動に明らかな影響が出ているとき、それはもう「気質」だけでは済まされないサインです。
たとえば、
気質→「気を使って疲れるけれど何とかできている」休めば回復する
病気→「緊張や不安で震えてしまい、どうしても行けない・できない」毎回同じ・もしくは不安が増していく
このように今まで普通にできていたことができなくなる、のが病気であるサインだと考えます。
注意したい具体的なサイン例
以下のような様子が見られたら、HSCの気質だけで済ませてはいけない段階に来ているかもしれません。
・電車やバスに乗ろうとすると動悸や吐き気がする
・学校に行こうとすると体が震える・過呼吸になるなど何らかの身体症状が出る
・非現実的な思い込みで、外に出られなくなったり、確認作業が増えたりする
・人の目を異様なまでに避けるようになり、行けない場所が増える
ある意味、学校に行けない状態は日常生活に支障をきたしていることになります。
不登校の場合には、こころの不調を抱えてる可能性を考え、上記のような症状がないか慎重に様子を見ましょう。
二次的な心の不調を引き起こさないために
HSCの気質は、不安障害などの心の不調につながりやすい面があります。
では、どうしたことがきっかけで、障がいとなってしまうのでしょう?
繰り返しになりますが、ポイントは以下の2つです。
・自己理解が進まず、自分を否定し続けている
・刺激の強い環境で無理をしてしまう
このような状態が長く続くと、心身に負担がかかり、病気へと発展してしまうことがあります。
つまり、
自己理解を深め、自分を肯定できること
安心できる環境に身を置くこと
が、病気になるリスクを防ぐカギなのです。
もちろん、常に安心できる環境にいられるとは限りませんが、「安心して過ごせる時間」を意識的につくっていくことは可能です。
たとえば、
・学校で疲れ切ったあとは家の安心できる空間でしばらくゆったり過ごす(習い事などを詰め込まない)
・土日どちらも出かける予定を入れない(1日は家で過ごす)
・昼寝の時間をとる
まずは、HSCの気質を適切に理解し、対処していくことが大切です。
学校での対処の方法についてはこちらの記事をご覧ください。
我が家の不安障害

うちの娘も、不安障害全般、その兆候が見られる時期がありました。
それは少し焦って、再登校を頑張ってしまった、その後のことでした。
「学校に行けない…」実はその時すでに、頑張りの限界を超えていたのに、しっかり休息を取らず、「家でもがんばり、学校でもがんばる」状態が続いてしまったのです。
安心感のない状態のまま我慢を重ね、エネルギーはすぐに枯渇。
再度学校に行けなくなったときには、娘は外に出ること自体が怖くなっていました。
そして頑張って出かけても、電車に乗ると一駅ごとに降りるようになってしまったのです。
その時は気が付かなかったのですが、あれは気質のせいではなかったと思います。
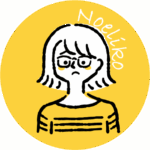
その前に、パニック発作もありました。
学校へ行くと胸が痛くて息ができない、と連絡が2回ありました。
その時にせめて気が付いていたらと思います…。
その後、娘は、休息する過程で強い不安症状はなくなっていきました。
そしてエネルギーがたまってからゆっくり段階を踏んで成功体験を重ねることで、半年で完全に回復しました。
あれからパニック発作は一度も起こっていませんし、今は電車に乗ることも平気です。
不登校になったらまず親は何をするべきか…今思うのはこんなことです。
病気かも?でも焦らなくて大丈夫な理由
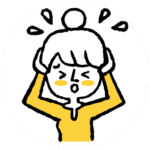
「HSCが、不安障害になりやすい?!」
「不登校ならすでになんらかの病気かもしれない?」
一気に心配になってしまったかもしれません。
しかし、慌てて受診する必要もありません。
実はHSCはHSCは環境調整で改善することが多いのです。
慌てて受診しなくても大丈夫な理由
慌てて受診しなくても大丈夫な理由は、HSP/HSCは、環境を整えたり、しっかり休息をとることで回復する力が強い子どもも多いからです。
・刺激から離れて静かに休める場所を作る
・感情を受け止めてくれる存在がそばにいる
・無理に「普通」に合わせさせない
こうした対応だけでも、一時的な不安状態が軽くなっていくケースは少なくありません。
HSCの子どもたちは、外に反応する力も強いのですが、実は内部に反応する力も強いのです。
とくに思春期は不安を感じやすい時期でもありますが、同時に思考力もぐんと成長する時期でもあります。
適切な対処とは
・ゆったり休息すること
・不安感じている事象そのもの(外に出れない、電車にのれない)ではなく、自分自身に対する不安を取り除いてあげること。
自分自身に対する不安を取り除いてあげる、のは、自己肯定感、自分軸と深く関連しています。

とても大切なので、こちらの記事で詳しく掘り下げいます。
ゆったり休息し、不安が和らいでいくようなら大丈夫ですが、場合を見て親御さんが不安を感じるようであれば無理をせず受診するのも、大切な判断です。

うちも受診は一度しましたが、通院はしていません。
受診する?しない?親が判断に迷ったときのポイント


「やっぱり早く受診したほうがいいのかな?」
「どのタイミングで行くべき?」
そう悩む親御さんも多いと思います。
心療内科やHSPカウンセリングは、「病気を治す場所」だけではなく、「病気にならないために気軽に相談する場所」でもあります。
判断するポイントは次の通りです。
・本人が行きたいという
もしくは
・今までできていたことができなくなり、日常的に困っている(休息したいのにできない状態である)
本人が行きたいという
まず、心療内科受診のハードルを上げないことが大切です。
気楽に相談できる場所であることを理解しておきましょう。
そのために、心療内科がHSCの名前を掲げて、窓口を広げているというのもあります。
そして行くことで本人が安心するかどうかを確認し、行きたいと言ったら尊重してあげるとよいと思います。
理解してくれる大人の存在は、HSCの子にとって何よりも安心感になります。話すだけで気持ちが楽になることも多いです。

逆に本人が行きたくなのに無理に連れて行くのもNGですね。
休息したいのにできない状態である
あとは親御さんが見ていて、気にする度合いが日常生活を脅かし、心や体が休まる場合ではないほど強く見えた時です。
休息したいのに、できていない…日常的になにか別のものに支配されているようなときです。
たとえば
・電車に乗れないだけでなく、外に出ることすら怖がっている
・外出してもすぐ帰りたがり、表情や言動に強い緊張が見られる
などの場合は、専門家の力を借りるタイミングかもしれません。
子どもに合う病院の見つけ方。HSC対応のポイントとは
以下が病院選びのポイントです。
| 病院選びのポイント |
|---|
| ・ホームページなどでHSPやHSCへの理解を示しているか ・子どもも診てもらえるか |
| 注意したい点 |
|---|
| ・初回で薬物療法を強くすすめてくるような場合 ・医師やカウンセラーとの相性が合わない場合 |
HSCの子は薬に敏感なことが多く、合わないと副作用が強く出てしまうことがあります。

うちの娘も、どんな薬は常に半量。
体の反応が敏感だからこそ、慎重さが求められます
また、最初はカウンセリングをすすめられることも多いですが、これも相性がとても大切です。
「合わないかも」と感じたら、遠慮なく変更して大丈夫です。
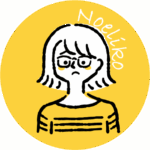
残念なながらいままでもHSCを知らないカウンセラーさんもいました
やっぱり心療内科は敷居が高い!でも不安!そんなときに頼りたいのがオンラインカウンセリングです
私も「うららか相談室」を2度ほど利用させてもらいました。
ただ「うららか相談室」はお医者さんによる診断はうけられないので、医療分野での判断が必要だと感じる場合には「かもみーる」のサービスがおすすめです
まとめ:「気質だから大丈夫」と思い込まずに
HSCやHSPの気質そのものは「病気」ではありません。
しかし、合わない環境で無理をすると、不安障害や適応障害などの二次的な心の不調を引き起こすことは少なくありません。
「気質だから仕方ない」と片付けてしまわずに、日常生活にどの程度の影響が出ているかをしっかり見つめることが大切です。
特に、学校生活で限界まで我慢した末に不登校になったお子さんの場合、慎重に様子を見ましょう。
私たち親にできることは、まず「安心できる環境を用意し見守ること」です。
まずは休息して、それでも不安症状が続く・強まるようであれば、迷わずプロの力を借りましょう。
心療内科や精神科は、「病気を治す場所」だけでなく、困りごとに耳を傾け、支えてもらう場所でもあります。
子ども自身が「誰かに話を聞いてほしい」「安心したい」と感じている場合は、迷わず扉を開いてみてください。

HSCが自己理解を深めると生きやすくなります。
こちらの記事もぜひご覧ください。