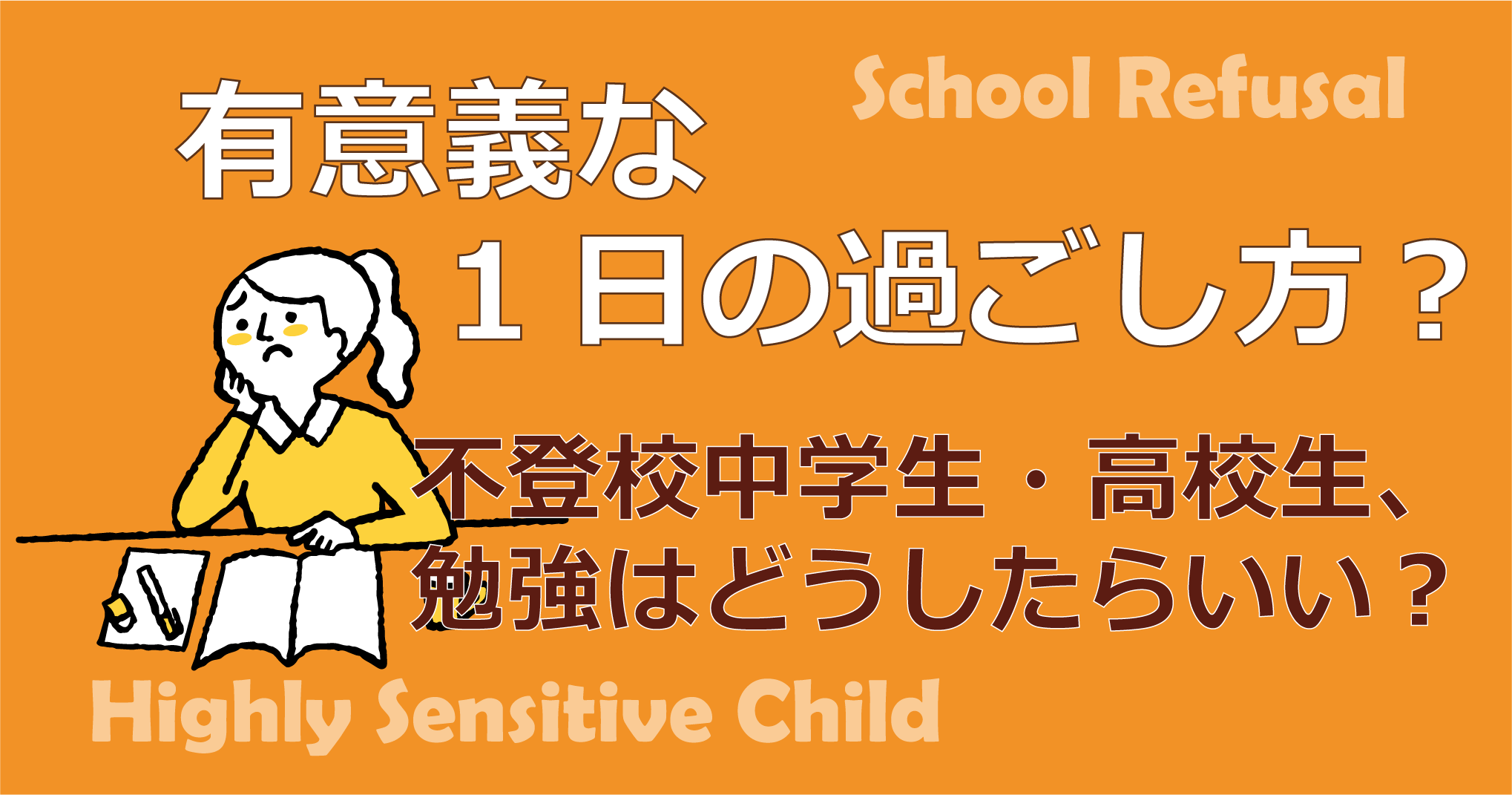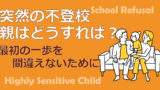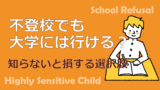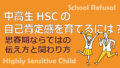勉強をしない不登校の過ごし方 ほおっておいて大丈夫?
不登校で家にいると、気になるのは過ごし方ですよね。

ゲームばかりしてる
昼頃おきてYouTubeばかり、、、
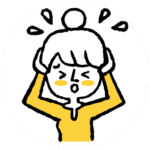
こんなんじゃ将来が本当に心配!
進学できないのでは?
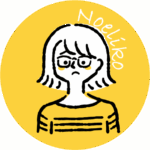
その気持ち、痛いほどわかります
しかし、まずは休息が大切です。
親の大きな仕事は安心のできる環境を整え、エネルギーが溜まるのを待つこと。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
何もしてない時間は何もできない時間だと思います。
そして、充分にエネルギーが回復すると、うごきだします。
そのタイミングで、将来のために学習することを勧められるといいですね
この記事では、「不登校で家で勉強しないわが子が心配」な親御さんに向けて、
・ストレスを減らして向き合うための考え方
・“やる気になったときにあきらめなくてすむ”ために今できる「勉強の素地」づくり
についてお伝えします。
心配な勉強 考え方を変えて気持ちを楽に
不登校の子どもたちには、たくさんの自由時間があります。
だからこそ、「少しでも勉強してくれたら……」と思ってしまうのが親心ですよね。
ですが、実際には自主的に机に向かう子は多くないのが現実です。
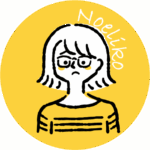
親もストレスが溜まりますよね
そんなときの考え方のヒントです。
学校じゃなくてホームスタディ
まず、「学校でないと勉強できない」という考え方は手放しましょう。
学校の授業がすべてではありません。
今は自宅でも学べるたくさんの選択肢があります。
「学校じゃなくても、学ぶことはできる」——この前提からスタートすることが、不登校の学びを考えるうえでとても大切です。
人生を逆算して勉強を考える
「なんのために勉強するのか」——この問いに、明確に答えられる人は意外と多くありません。
将来のため?
いい大学に入るため?
いい会社に入るため?
そう考える方も多いですが、突き詰めれば、「よりよい生活を送りたいから」という想いが根底にあるのではないでしょうか。
では、「よりよい生活」とは何でしょうか?
高収入を得られる企業に入ること、安定した職業につくこと、自由な働き方を手に入れること…。
人によって、その答えは違います。
つまり、「よりよい生活」から逆算して進路を考えることが大切なのです。
“とりあえずいい大学”ではなく、どんな人生を送りたいかを出発点にしてみる。すると、今すべき勉強が見えてくることがあります。
たとえば…
カウンセラーになりたい → 今の不登校の体験や人の心への理解が、将来の糧に
建築士になりたい → 建築物を観察したりスケッチしたりすることが今の学びに
絵本作家になりたい → 絵を描いたり物語を作ったりする時間が「勉強」になる
プログラマーになりたい → YouTubeで基礎知識を学んだり、タイピングを練習したりすることが第一歩
こうした視点で考えれば、今机に向かっていなくても「学び」は始まっています。
勉強=テストの点を取るためだけのものではありません。
よりよい生活に近づくために、何を学ぶべきかを考えることこそ、いちばんの勉強かもしれませんね。
学習は生きる力をつけるためと考える
「将来どうしたいかまだわからない」——そう感じている子どもは多いものです。
でも、将来の夢が決まっていなくても、今できる“学び”はたくさんあります。
勉強とは、単にテストで点を取るためのものではなく、“よりよく生きる力”を育てる手段でもあります。
そしてその力は、必ずしも机の上だけで身につくものではありません。
たとえば——
水族館で不思議に思ったことを調べてみる。
料理に挑戦して、失敗を改善してみる。
映画を観て、登場人物の気持ちを想像してみる。
そんな一見「勉強」とは無縁に思える体験こそが、思考力・想像力・表現力といった“生きる力”を育ててくれるのです。
今の教育では、こうした日々の学びや自発的な体験が大学入試(とくに総合型選抜)で評価される時代になってきています。
実際に、不登校の時間に取り組んだ活動や興味関心が、進学や就職のアピール材料になることも少なくありません。
すべての経験が学びになり、大学(総合型選抜)や就職にもつながる。
そんなふうに考えられるようになると、不登校の期間も「ただの空白」ではなく「意味ある時間」に変わっていきます。
可能性を広げるための、「勉強」高校ではなく大学を考える
一方で、将来の選択肢を広げるためには、机に向かう勉強もやはり大切な要素であるとこは否めません。
勉強しておけば、もし、急になりたいものが見つかっても、軌道修正しやすいことは確実です。
その場合でも、高校じゃなくて大学(最終学歴)を見据えて勉強を始めましょう。
いい高校に行けばいい大学に入れる確率は高くなります。
しかし今学校に行けていないのなら,再登校からの勉強までの時間的猶予が短く、気持ち的にとても焦ってしまいます。
親の焦りは、子どもの負担やプレッシャーになります。
もちろん、あとになればなるほど、巻き返すのは楽ではありません。
しかし、慌ててしまうとかえって逆効果となり心の回復が遅れて、勉強ができる状態になるまでの時間がかかってしまう可能性があります。
まずは、子どもの「心のエネルギーの回復」を最優先に考えましょう。
親が「大学入学で十分巻き返せるから大丈夫」という気持ちでゆったり構えることが、子どもにとって何よりの安心材料になります。
こちらの記事も参考にして下さい!

本当に焦らなくても大丈夫です!
今できることは、将来のための「土台」をつくることです。
次の章では、やる気になったときにスムーズに学びを始められるための“勉強の素地”についてご紹介します。
勉強するじゃなくて学習の素地を作る
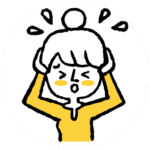
回復してから?
それで間に合うの?

どんどん置いていかれて不安になる!

その不安、わかります。当然のことですよね
ただ、勉強の気力がわかないときに無理やり机に向かわせてもいい結果は得られません。
場合によっては勉強への苦手意識が増してしまうことにもなります。
勉強することそのものが学校を思い出しストレスとなる場合もあります。
そんな時は勉強ができる状態が来たとき、追いつけるような素地を作るだけでよいと考えていきましょう。
この素地があれば、ヤル気になったとき、今からでは間に合わないと諦めなくてすみます。
今できなくても焦らなくても大丈夫!勉強ができる素地とは
勉強ができる素地とは、“学ぶ準備”を整えることです
次の3つの力のことを指します。
| 1. | 学力を伸ばすための「思考力・判断力・表現力」 |
|---|---|
| 2. | 勉強の効率を高めるための「暗記力・集中力」 |
| 3. | 勉強に対する苦手意識を減らす「読解力・英語力」 |

その理由と、やり方を詳しく解説していきます!
学力を伸ばすための「思考力・判断力・表現力」
学力を担保するものとはなんでしょう。
それは、大きく以下の3つです。
基礎学力、
それを活用できる思考力、判断力、表現力、
学習態度(意欲)
不登校の今、基礎学力が不足してしまうのではと心配になりますよね。
そして、学習意欲も下がっている状態でしょう。
それなら今は、基礎学力にとらわれすぎず、「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことに注力してみましょう。
物事一つに対して、自分で深く考える力は、今後の受験においてとても重要な能力となってきます。
社会問題について語れる必要はありません。もっと身近なことで大丈夫です。
好きな映画、ドラマ、まんがについての感想を語る、それだけでも十分です。
よかったなぁ、好きだなあだけでなく、
・なぜいいと感じたか、
・なぜ自分は惹かれたのか、
深堀りして考えていく、そうしてそれを相手に伝えられる能力を鍛えていきましょう。
また、さまざまな経験をすることも、脳が刺激をうけ、思考力、想像力を鍛えることになりますよ
勉強の効率を高めるための「暗記力・集中力」
さらに勉強の効率を高めるために必要なものが2つあります。
・暗記力
・集中力
集中力がない、暗記が苦手といいますが、この2つに関してはトレーニング、訓練すれば伸びてきます。
ただ集中すること・暗記することに慣れていないから難しいという場合も少なくないのです。
暗記
暗記系のゲーム(神経衰弱・単語カード・クイズアプリなど)を取り入れてみましょう。
K-POPが好きなら、推しの韓国語を覚えるのも立派な暗記トレーニングになります。楽しさと結びつけることがポイントです。
どうしても暗記ができないと嘆く子がいたら・・
認知特性を知りましょう。
認知特性とは、物事を脳で整理し理解することで、最終的に知識となるまでの五感の経路によって「視覚優位者」「言語優位者」「聴覚優位者」の3つに大きく分類されます。
自分の脳が「どの感覚を通して情報を処理するのが得意か」を理解すれば、自分に合った暗記方法を選べるようになります。
例えば視覚優位なら絵や図をかいて覚えたり、聴覚優位なら声に出して繰り返し聞くことで覚えたり、言語優位なら文章からイメージして覚えたりすると効率的です。
これだけでもかなり暗記する際の助けになります!詳しくまた記事にしたいです
集中力
好きなものに集中することができるなら第一関門は突破といえるでしょう。
嫌いなものにどれくらい集中して取り組めるかどうかが第二段階です。
具体的な方法としては
マインドフルネスが有効です。
目を閉じて、2分ほど「自分の呼吸」にだけ意識を向けてみましょう。
雑念が浮かんでもOKです。そのたびに意識を呼吸に戻す練習が、集中力を高める訓練になります。
マインドフルネスには気持ちの安定する効果もあります。
ただ、気持ちがまだ本当に不安定なときはマインドフルネスができない場合がある(目を閉じてじっとしてると、不安が襲う)のでそこは無理強いすると良くないため慎重に。
その場合心の病になっている可能性も考えて見守っていきましょう
こちらの記事をご覧ください
勉強に対する苦手意識を減らす「読解力・英語力」
最後に、基礎学力のさらに土台となるものです。
読むことと英語への抵抗感をなくすことが大切です。
読むことへの抵抗感をなくす
勉強を始めると多くの活字を読むことになります。
慣れていないとこれだけでストレスになったり字面をなぞるだけで頭に入ってこなかったりします。
実際、「読むことに抵抗がない子」は、学習のスタートでつまずきにくい傾向があります。
まずは読むことへのハードルは下げておくことが重要です。
読むという行為を日常的にしていると安心です。
たとえば
SNSに制限を設ける一方で漫画や本なら読んでいいよ、といってみるのはどうでしょうか?
とくにHSCは想像力が豊かで感受性が高いので読書が好きな子が多いようです。今興味がなくても好みの一冊に出会えば積極的に読むようになると思います。
英語への抵抗感をなくす
あとは、英語への抵抗感もなくしておくとすんなり勉強に入ることができます。
理系でも文系でも、最後までついてくるのは英語です。
逆に英語一つ得意であれば、それを武器に合格できる大学も存在します
英語への苦手意識が強すぎると、学習を始めるときのハードルが高くなってしまうこともあります。
まずは「慣れる」ことから始めてみましょう。
英語に触れる機会を意識的に増やしましょう。
いわゆる勉強でなくても英語の音楽、映画を楽しむだけでも十分です。
英語の歌詞は、語彙やリスニング力を育てるうえでも非常に役立ちます。
学力ゼロからでも、あとで伸ばせる。だから今は“準備”が大切
学習意欲が芽生えたときに困らないように――
そのために今は、「思考力・判断力・表現力」「暗記力・集中力」「読解力・英語力」といった、“学びの素地”を整えておくことがとても大切です。
この3つの力があれば、たとえ学力がゼロの状態からでも、あとは**“量×質”**の努力で巻き返すことができます。
**“量×質”**の勉強とは「量=勉強時間」×「質=必要な内容に特化する」の勉強です–
「がんばっているのに伸びない」状態にならないように、やることを厳選する勉強、「量×質=効率よく結果につなげる」勉強法です。

これについてはまた今後記事にしていきますね
もちろん、早く始めるに越したことはありません。
けれど、心がまだ整っていないうちに無理に勉強させようとすると、逆効果になることもあります。
まずはしっかり休むこと。
回復の時期を削らないことが、結果的に勉強につながる近道になります。
勉強は、必要なときに必要な形でちゃんと向き合えばいい。
焦らず、でも諦めず。
そんな気持ちで、親として今できることを積み重ねていきましょう。