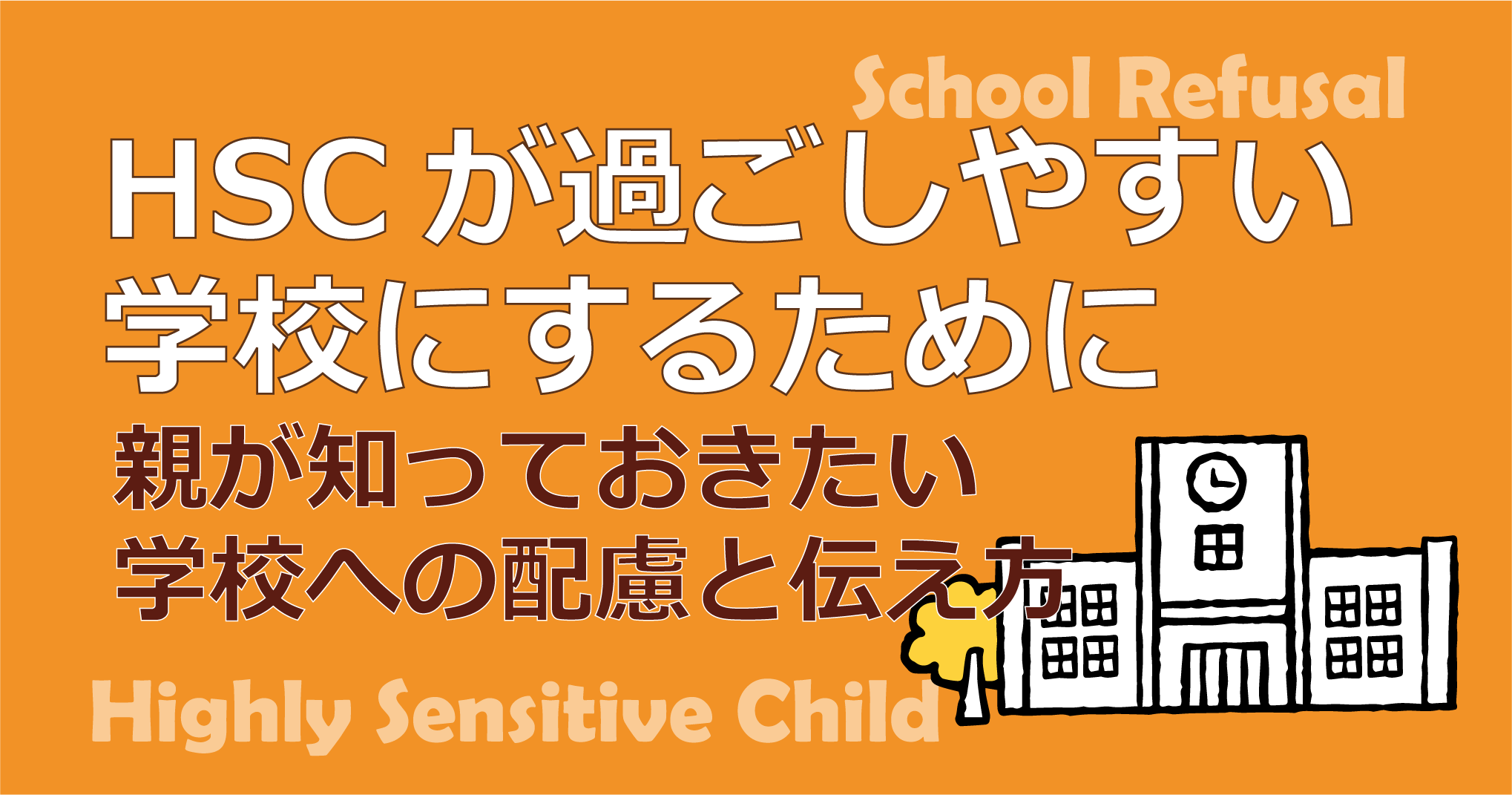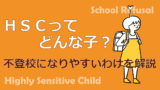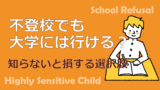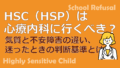学校がつらいHSC
HSCは五感に対するあらゆる刺激にとても強く反応します。また、人の感情にもとても敏感です。
そんなHSCにとって、刺激が常にあふれる学校はとてもしんどい場所です。
しんどい場所で無理を重ねた結果、不登校になることは珍しくありません。
HSCの特性や学校が苦手な理由はこちらの記事で詳しく解説しています。
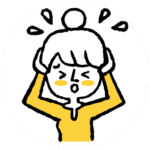
「HSCは学校が苦手というけれどどうしたらいいの?」
「再登校するためにはなにをしたらいい?」
お子さんの不登校の原因がHSCだと気付いた親御さんが次に考えるのはそうしたことでしょう。
学校で、どうすればHSCが負担なく過ごせるのでしょうか?
そんな疑問や不安に対して、この記事では【HSCに必要な“配慮”とは何か】【学校への伝え方の工夫】を、実例を交えながら解説していきます。

そして、学校を過ごしやすくするために一番大切な自己理解についても触れています!
HSCの学校生活に“配慮”は必要?

学校を「しんどい場所」にしないために、まず考えるのは、学校側に配慮を求めることでしょう。
HSCにとって学校は刺激の多い場所です。
その刺激が緩和されれば、かなり過ごしやすくなるはずです
しかし、HSCは音・匂い・光・人間関係など、ほとんどの刺激に敏感に反応してしまいます。
たとえば大きな音がストレスなのでイヤホンや耳栓の使用を許可されたとしても、それはほんの一部の刺激から遠ざかったにすぎません。
また特別扱いされることでの弊害もあります。
学校での配慮は「必要」ではあるとは思いますが、その内容や伝え方は慎重に考える必要があるでしょう。
HSCが必要な配慮とは?まずは子どもの気持ちを聞く

親は、HSCがさまざまな事象でつらい思いをしてると知れば、それをできる限り取り除こうと考えます。
そして1日の大半を過ごす学校においても、それを求めるのは自然なことです。
しかし、親が心配で焦り、配慮を求めることを急ぐとさまざまな問題が起こります。
HSCの思いを置いてきぼりにせず、どういった配慮がよいのかを考えていきましょう。
「特別扱いされたくない」HSCの本音
大前提としてお伝えしておくと、HSC自身は目立つ配慮を望んでいないことが多いです。
それは、
・配慮によって浴びる好奇の視線も刺激である
・他のこと違うことが浮き彫りになり、かえって傷つく
こうした理由からです。
親御さんとしては

「どうして?お願いしておけばだいぶ楽になるかもしれないよ」
と前向きに提案することもあるでしょう。
そうした不安な親の気持ちまで敏感にくみ取って、本当は嫌でも「No」と言えなくなってしまうHSCもいます。
まずは「特別に配慮されること」は嫌であると考えて話をすすめていきましょう。
子どもの思いにしっかり耳を傾ける
HSCは、自己主張することが苦手です。
自分のことを語ろうとすると、涙が出てくるHSCは珍しくありません。
娘もそうです。
話している自分のつらさに共感してしまうのか、やっと言えたという安ど感からか、はたまた聞いてくれる相手への申し訳なさからなのか----
本人も理由はわからないようですが、自分の気持ちを語ることはそれほどまでに感情を揺さぶられる行為なのです。
そんなHSCは親にさえ気持ちを説明することは難しいと感じています。
まずはしっかり時間をかけて、子どもが学校において何を求めたいと思っているのか話を聞くことから始める必要があると考えます。
「特別な配慮」がうむ懸念点
親が子どもを心配するあまり学校に過剰な配慮を求めすぎてしまうと、子ども自身や学校環境にとって「弊害」が生まれることが懸念されます。
特別扱い嫉妬心や嫌悪感嫉妬心や嫌悪感
まずは、特別扱いについて、周囲の理解を得られないことによる弊害です。
HSCは普段頑張っている分、少し恥ずかしがりやかな?程度の認識はあってもとくに苦労をしているようには見えません。
そうした中で特別扱いをあからさまにされてしまうと、なぜあのこは特別なの?という周りの違和感は、嫉妬心や嫌悪感を抱かれる原因になります。
ただでさえ穏やかに過ごしたいHSCにとって、それは最悪ともいえる事態です。
HSCのイメージの悪化で周囲からの理解が遠のく
過剰な配慮を求めることのもう一つの弊害はHSCそのもののイメージの悪化です。
実行の難しいことや極端な特別扱いを求める、またはささいな配慮でも当たり前だとする態度でいると、「HSCってこういう厄介な存在」というイメージを持たれかねません。
そうすると、本来のHSC概念の理解が進まない要因にもなります。
「自称HSP/自称HSC」という存在が生み出したネガティブなイメージと重なり、「HSC=扱いづらい/面倒な子」という偏見を強化する結果になってしまうのです。
こうしたことにならないよう、話を聞き本人の思いを尊重することが大切です。
本人の求める範囲を超えない配慮を求めていきましょう。
「自称HSP」とは、以下のような人に向けられたネガティブなニュアンスの言葉です。
HSPを名乗ることで:
・嫌なことを避けたいと主張する人
・強く特別扱いを求める人
HSPは、人に気を使いすぎて、自分に必要なことを伝えられない」という苦しさを抱えています。
HSPであることを主張して特別な配慮を求めることは、「本物」には難しいと考えます。
求めるものはHSCの特性に対する理解

結局正しい配慮の求め方ってなに?
子どものための配慮ってどんなものなの?
たしかに、
・イヤホンの使用を認める
・静かで落ち着ける席を選べる
・一人になれる静かな居場所を確保してもらう
・いつでも休憩できる特別な許可をもらう
そうした特別な配慮があれば、教室の刺激は回避できる場面も多いでしょう。
しかし、そうすることがHSPに対する偏見や好奇の目などでHSCが違うつらさを感じるようになってしまったら・・・それは意味のないことです。
結果的に思うのは物質的な配慮よりも困ったときに「それがつらい」と言える雰囲気を作ることを求めた方がよいと考えます。
それは、HSCの特性に対する、優しい理解です。
そしてそれを、多くのHSCは望んでいると思っています。
配慮を求めるより必要な自己理解

やさしく理解してもらったところで、刺激は避けられないのでは?
根本的な解決になっていないのでは?
そのご指摘はもっともです。
基本的に、あらゆる強い刺激に対して、HSC自身が対処できる力をつけることが大切だと私は思っています。
そもそもHSP/HSC概念は、「自分を知るツール」であって、配慮を要求するラベルではないという大前提があります
アーロン博士がこの概念を提唱した背景には、以下のような目的がありました:
「敏感で繊細な性質は異常ではなく、“生まれ持った特性”であり、自然な個人差のひとつである」と示すことで
・HSPの人たちが自分の特性を理解し、「自分はダメな人間ではない」と感じられるようにすること
・HSPの人たちが自己理解を深め、日常生活でのストレスを減らすこと
そうしたなかでHSPやHSCが社会との関わり方を見つめ直すことができるようにとアーロン博士は考えました。
自分で状況に対処できる力を身につける大切さ
HSP・HSCはの世に20%程度でマイノリティです。
そのマイノリティに合わせて社会が変わっていくとは考えにくく、またそれを求めるのもとても難しいことと思います。
当たり前に配慮される世の中になってほしいというのは過度な要求のように感じます。
マジョリティである非HSPが生きづらい世の中になってしまう可能性があるからです。
世の中をスムーズに動かしていくために、許容範囲を超えてまでも配慮を求めるのは違うでしょう。
これからHSCは、学校以外のさまざまなコミュニティとかかわる機会が増えていきます。
そのときに「周りが配慮してくれない」と嘆くよりも、自分で状況に対処できる力を身につけることの方が、ずっと大切で意味のあることです。
学校でできる具体的な自己対処方法
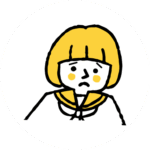
学校で自分でできる対処法って何?
では学校ではどういった対処を自分ですることが可能でしょうか?
娘の例です。
・一人になれる心地のいい場所を見つける
小学校の頃は誰も来ない、一人に慣れる隠れ家のようなスペースを見つけて、休憩時間疲れたらそこで過ごしていたそうです。
・休み時間に読書をする
大好きな本を想像力を働かせながら読むことで、学校での息苦しさを紛らわせようとしました。
また合理的に人から話しかけられない状況を作れます。
・伊達メガネをかける
他人と物理的な境界線を視界に作ることで、他人の感情をシャットアウトするきっかけを作っています。
・好きな香りのハンドクリームをつける(校則範囲内)
落ち着くにおいをまとうことで、他の刺激をシャットアウトする効果を狙っています。

これは娘の例ですが、多くのHSCにも有効であるのではと考えます。
誰かのヒントになればうれしいです。
もちろん、一人ひとりの個性によって、自分なりの方法を模索していく必要があります。
感じ方は、HSCのなかでも個性があります!
たとえばうちの娘は、音の過敏性はありますが、小さい頃から雨の音は好きで、よく聞いていました。
しかし、友だちのHSCくんは、雨の音が怖いと泣いていたそうです。
自分を許せる自己理解を深めることも大切
自分で対処できるようになるために、一つ重要なポイントがあります。
ある程度の心の「余裕」を持つことです。
心の余裕とは、「まぁいっか」と考えることです。
HSCにはそれがなかなか難しく「しんどかったら休んでいいよ」と言われても

「そんなことしたらどんな風に思われるのかな」
「みんなも頑張ってるのに1人休めない」
と不安になってしまいます。

「やすんでもまぁいっか」
そう言えるこころの余裕をもてるように、声かけしていきましょう。
・つらくなったら帰ってきてもいい
・しんどかったら休んでもいい
・休み時間もずっと誰かといなくてもいい
・みんなと無理に仲良くしなくてもいい
それはあなたに必要なことだから、けして悪いことではないのだよ
目が悪かったら眼鏡をかけるように、認められてよいことなんだと、伝えてあげることが大切です。
そして、それを認められるように、HSC自身変わっていけると安心です。

自己理解がHSCを生きやすくします。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
どう伝える?学校とのコミュニケーションの工夫

自身で対処をすればいい、と言っても、やはり学校を過ごしやすくするためには、学校のサポートも必要になってきます。

「学校に求める配慮は具体的にどういうものがいいの?」
それは物理的な配慮より、困ったときにHSCが「それがつらい」と言えるよう、理解してもらえることをまず目指していきましょう。
ここからは具体的な伝え方のコツに焦点を当てていきましょう。
自己対処に必要なものの許可をとる
まずは自分で対処できるかどうか、できるようならそれがスムーズに叶うように理解を求めましょう。
たとえば、伊達メガネ。
本当に視力が悪くないなら、かけることは認められないと思います。ファッションだととらえられてしまいます。
そうしたことへの説明は一番に考えるべきことです。
もし、よりどころとしてたアイテムの存在をとがめられるようなことがあったら、HSCはそれを持っていくことを永遠に拒むでしょう。
そうならないように、校則の範囲内で目立たない許されるものであっても、伝えておくと安心です。
本人の「つらい」という思いを共有する
そして次に「配慮してください」ではなく、「こういう子です」と共有するスタンスを意識しましょう。
必要性を感じないならHSCの概念の説明までする必要はありません。
あくまででこういうことに困っていて、こういうことが難しい子です、ご理解いただけると嬉しいです、と具体例を挙げて伝えるとよいと思います。
それは
・“わがまま”ではないこと、
・外からはわかりづらく本人も遠慮がちに言うと思うけれど、“本当にしんどい”と感じていること
を理解しておいてもらいたい、と伝えてみましょう。
HSCの希望に配慮のお願いをする
きちんと子ども話を聞く中でどうしても無理なことがあったとしたら、それだけは配慮としてお願いしてもよいと思います。
娘の場合は、テストの際、廊下側の席であると、刺激になるものが多く集中できないため、テスト時の座席だけ配慮をお願いしています。
娘はもう高校生なので自分で伝えています。それも自分の力で対処する練習だなと思っています。
HSCが考え、選択し、それだけはお願いしたい、と言う事だけでいいと思います。
というよりむしろ、それ以外のことを先走ってお願いしてしまうとHSCは心苦しさを感じてしまうので避けた方がよいでしょう。
伝えにくさ・伝わらなさの壁とどう向き合う?

「学校に伝えようと思うけれど伝わらなくて」
「診断書を出してと言われてしまった」
「担任がHSP/HSCを知らなかったので説明が難しかった」
次に直面するのはそういった問題でしょう。
HSCは病気ではないので診断書がありません。
また、その気質の性質上、説明が難しく、誤解をまねいてしまうこともあります。
HSC気質が理解しづらい理由
説明の難しさはその本質が一般の人にわかりづらいということがあります。
HSPの本質は、「刺激に対して非常に敏感であること」です。
敏感であることで、とてもしんどかったり、つらかったりします。
そうしたHSPの「つらさ」が、とても伝わりにくいのです。
非HSPの人からすれば「そんなことで?」と思うことも多く、言われても実感がわかないためです。
例えばある人が「高いところがだめなので、行きたくない」というとします。
その場合、”高いところはそもそも危険で怖い場所”という認識があるので、その人が感じる恐怖を想像できます。
なので、自分が平気だとしても、だめだ、と言われたらほとんどの人がすんなり受け入れることができます。
しかし、HSPさんは、「太陽の日差しが強く、窓際の席はつらい」といったことをいいます
「強い日差しは誰もが嫌ではないのだろうか?」 もしくは、 「そんなことがつらいの?」 という反応をする人がいるのではないでしょうか。
なぜならつらい感覚を想像してみても、それは「席をかわるほど」つらくないからです。
人は、自分の想像しうる範囲でしか物事を推し量ることができません。
日差しがつらいという感覚。大きな音が怖いという感覚。
非HSPたちの物差しはHSPの感覚を図るメモリを持っていないのです。
本人にしかわからない「感じ方」がHSPの本質にかかわっているため、本当につらく感じているのか真偽の判断が難しいのです。
そしてそれを証明するすべがありません。
病気ではないため医師の診断するものではないからです。
またこの「病気ではない」「個性の一つである」という正しい認識も、じゃあ特に配慮なんていらないんじゃないの?と非HSPを混乱させてしまいます。
親がHSCを説明できる力を持つことが大事
親には理解しづらい気質の本質がきちんと伝わるように説明する力が求められます。
以下がそのコツです。
事例をもとに伝えることを意識する
できるだけ具体的に何がどう苦手なのかを伝えましょう。
漠然とすればするほど、先生は何をしたらよいのかわからなくなります。
たとえば
「運動会でピストルの音にとても恐怖を感じ、走れず立ちすくんでしまいます」
「人がひしめきあっている朝礼前の靴箱がとても怖いようです」
「発表の時手を上げるのを促されると、冷や汗をかくほど苦痛なようです」
などです。
HSCなので大きな音が無理です、と言われても、どの音が大きいのか、わかりません。
人混みが苦手です、と言っても、それはみんなそうなのでは?と思われてしまいます。
具体的にどういうふうになって(感じて)無理なのか、伝えるとよいと思います。
想像できるたとえ話を活用する
想像ができないから、その感じ方が分からないのだと、先にも述べました。
娘は自分のつらさを話すとき、私にわかるようにたとえ話をよく使ってくれます。
「まわりが不機嫌だと、自分がずっと誰かに睨まれているように感じて気持ちが落ち着かない」
「私にとって学校は、柵のない屋上。そこでずっと苦手なドッジボールをしてるようなもの」
これなら非HSPであるわたしも「そんなに!」と理解が及びます。
もちろん、大げさでは?と言われる可能性もあるのですが、ただ単に人よりつらく感じるみたいで、というより伝わると思います。
感じ方のすり合わせについては家で練習できます!
スクールカウンセラーなど、専門家・心理士に力を借りる
どうしても難しい時はプロの力を借りましょう。
この概念もうまれて30年になります。
残念なことに、であったカウンセラーの中でも、HSCの概念を知らないひとはいました。
しかし、一般の人たちよりは理解が深い人がいるのは確かです。
そういった方の助言を得て、説明することも有効です。
マタニティマークと似てる?HSCへの配慮の求め方
こうして考えていくと、ふと、HSCが求める配慮はマタニティマークが求めるそれと似ているなと感じました。
マタニティマークとは、まだお腹の大きくない見た目には妊婦とわからない人がつけるものです。
妊娠初期で身体の変化やつわりでつらい、さらに赤ちゃんがお腹の中でまだ不安定、そうしたことを、こちらがわかるよう視覚化したものです。
HSCもマタニティマークを付けた妊婦さんも、思いやりの範囲での理解と配慮を求めています。
マタニティマークを付けている人を見たら電車で席を譲ったりタバコを吸うのをやめたり…、そうした妊婦への思いやりのある行動をとろうとします。
同じようにHSPは刺激に敏感と聞いたからうるさい場所が苦手なんだな、そっとしといてあげよう‥そういう配慮があるとありがたいなと思っています。
「今ちょっと無理なんです」と伝えたときに、「あ、そういう子もいるって聞いたな」と少しでも思ってもらえたら…それだけでHSCはぐんと生きやすくなります。
その弊害についても似たようなものを感じます。
お互い病気ではないこと、
つらさが見て目にはわからないこと
そして自身が体験できなずその大変さが想像が出来ないこと、
そうしたことで、「マタニティマーク」や「HSP」を盾に大げさに配慮しろとアピールしていると誤解されてしまいます。
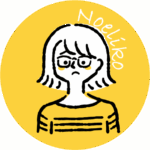
どちらも認知が広がり、悲しい思いをする当事者が減ることを祈ります。
それでもやはり学校はつらいもの
最後に、「学校を楽にいかせてあげたい」と努力している親御さんをがっかりさせてしまうかもしれませんが…
HSCにとって学校はやはりつらい場所です。
配慮や対処がないといけない場所であることは変わらないのです。
それをしっかりわかってあげて欲しいと思います。
週休3日なら何とかというならそれを尊重してあげて欲しいし、休みたいと言ったら休ませてあげて欲しいと思います。
無理をさせ過ぎると、精神疾患へつながってしまう可能性もあります。
「学校に行く=正解」ではない道もあっていいのではないか、HSCが学ぶ場所を別に求めてもいいのではないかと、個人的には思っています。

うちの娘も学校へ行く日を自分で選択して通っています。
まとめ:HSCにとっての“ちょうどいい配慮”とは
HSCの子どもが学校で少しでも心穏やかに過ごせるようにするために親ができることは
・子どもの言葉をていねいに聞くこと
・必要に応じて本人の代弁をすること
・そして“自分で守る力”を少しずつ育てていくこと
です。
学校に求めるべきは特別な配慮ではなく「声を拾ってくれる関係性」です。
目指すべきは「楽しい学校生活」ではありません。
「なるべく安心できる学校生活」です。
記事の冒頭に学校で、どうすればHSCが負担なく過ごせるのでしょうか?と問いかけましたが、負担が全くない場所にすることはほぼ不可能だと思います。
楽しく通って欲しいと願うことは親としては自然ですが、HSCにとってどう頑張っても学校はしんどい場所である可能性が高いです。
HSCが本当につらいときにSOSを出せること
それを目指して学校にマタニティマークのような思いやりの範囲で配慮を求めていきましょう。
世の中のHSCへの「自然な理解」が最大の配慮だと思います。
そして、もし学校以外の場所で自分らしくいることをHSCが求めてきたとしたら、親としての葛藤はあると思いますが、尊重してあげて欲しいと思っています。
学校に通わないことは、社会の道から外れることではない、そう思えるためには、まずは不登校はだめなこと、という考えから離れていきましょう。